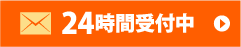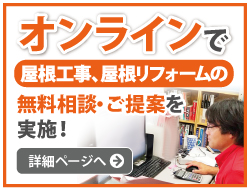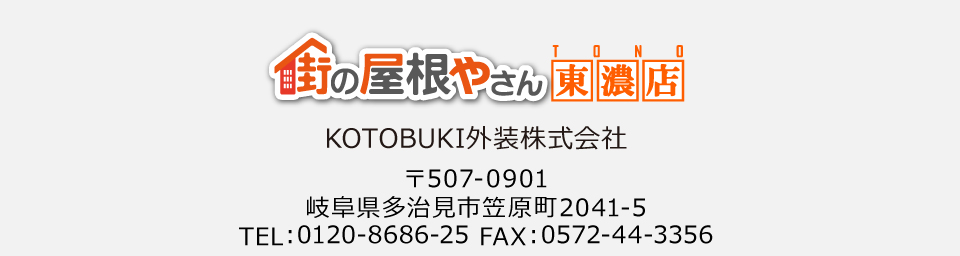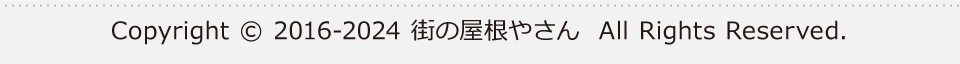瓦のずれはなぜ起こるのか?
主な原因は土葺き(つちふき・どぶき)と呼ばれる工法にあります

土葺きとは?
昔の瓦屋根は「土葺き(つちふき・どぶき)」と呼ばれ、瓦の下に土を敷いて葺く工法で作られています。瓦と屋根地の間に土が入っているので、屋根が重いのが欠点といえます。
構造は?
基本的な構造は、野地板(バラ板)の上に杉の皮などの下葺き材を敷き、その上に粘土を乗せ、その粘土の接着力で瓦を固定していく工法です。
土葺きの中でも、べた葺きと筋葺きがあり、べた葺きは野地板全体に土を敷き詰めて屋根を葺いていきます。筋葺きは瓦の谷の部分に当たる箇所に土を敷きます。土を筋状に置くことから筋葺きと呼ばれています。
べた葺きに比べると、多少屋根の重量が減ります。
土葺きは、土の下地に瓦を載せているだけで、瓦自体は一切どこにも固定していません。年月が経過すると土と瓦の剥離が起こり、剝がれやすくなってきます(ずれの発生)。よって地震には弱くなります。
土葺き工法が使われなくなってきたのは、関東大震災後と言われています。震災の際に土葺きの屋根瓦が落下して多数の被害が出たために、以降は使用を控えるようになりました。
関西でも阪神淡路大震災以、新しい工法が普及しました。「
引っ掛け瓦桟葺き工法」が主流になっています。「ひっかけかわらざんぶき」と読みます。
 引っ掛け瓦桟葺き工法
引っ掛け瓦桟葺き工法とは、桟木に瓦を引っ掛けて葺く工法をいいます。
瓦一列に対し「
桟木」と呼ばれる細長い木の棒を打ち、
瓦一枚一枚に釘打ちをします。 土葺きと大きく異なる点です。
土葺きでは、瓦を泥の上に載せているだけの状態ですが、引っ掛け瓦桟葺きでは、一枚一枚が釘で固定されています。これにより、瓦を固定する力が強くなっています。
土が使用されない分屋根の重量も軽くなります。
現在の新築の瓦屋根はほとんどこちらになります。

瓦の
ラバーロック工法とは、瓦と瓦の隙間をコーキングで接着してくっ付けてしまう工事の事です。つまり耐風性や耐震性が向上する効果が見込めます。
技術的にも簡単で、また工事の日数も短くて済みますから、工事にかかる費用・施工費が安く抑えられるという利点はあります。
瓦のずれを自分で直すことは、高所作業になりますので、
とても危険です。是非業者にご相談ください。
また特に土葺きの瓦屋根は、比較的古い屋根であることが多く、屋根リフォームをご検討いただくケースが多いです。
考えられる処置としては、
①
屋根の葺き直し工事(防水紙や野地板を交換・補修してから、これまでの屋根材を再利用して屋根を葺き直す工事)
②
屋根の葺き替え工事(
これまでの屋根を解体・撤去し、新しい屋根材に葺き替える工事)分かりやすくご案内していますので、一度お読みください。
8時~17時まで受付中!
0120-8686-25