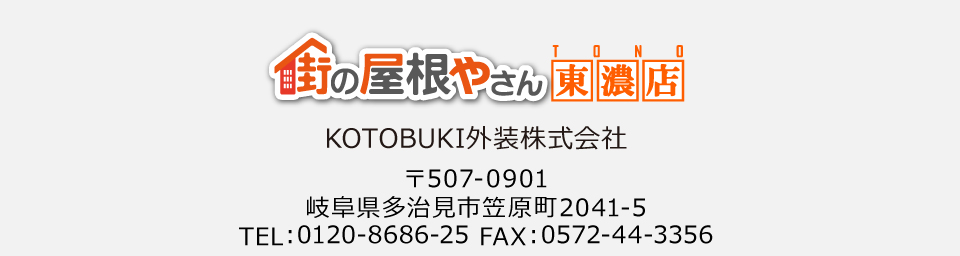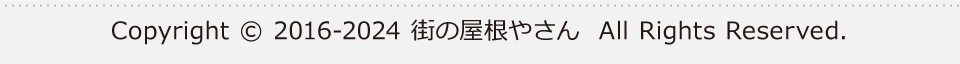2025.11.24
皆さん、こんにちは! 街の屋根やさん東濃店です。瑞浪市にある店舗にて、外部からの衝撃により破損した外壁を一面張り替え工事しました。建物の外壁は、車や搬入機器の接触、強風で飛来した物などの「外部からの衝撃」によって破損してしまうことがあります。破損とは、外壁の表面材がへこんだり、割…
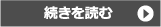
皆さんこんにちは。街の屋根やさん東濃店です。
可児市のアパートの外壁の汚れの現地調査を依頼されました。

こちらが現場の外壁です。
外見でもかなり汚れが目立ちますが、大きな特徴としてサイディングの塗装の剥がれががありました。これがある場合は内部の通気性が悪く、湿気が溜まって内部結露をしている可能性が高いです。
結露については、以前のコラムでもご紹介したことがありますが、現在の建物は断熱材が使用されており、水蒸気を多く含んだ空気は、通気性のない断熱材の中を移動しようとして、その際に断熱材内部に水分が溜まってしまいます。これが内部結露になってしまうのです。
しかし、このようなことが起きないように、通常、サイディングと外壁の間に通気層や防湿層が作られます。
≫(コラム)結露とは
通気工法とは、サイディングと外壁の間を空気が流れるような作りになっており通気性が確保されています。反対に、直貼り工法の場合はサイディングと外壁の間に隙間がなく、通気性が悪いので、湿気がこもりやすく表面が剥がれてきてしまいます。
通気工法か直貼り工法かを見極めるポイントとしては、外壁と基礎の間に水切り板金があるかどうかを確認すればわかりますが、水切り板金があっても隙間が狭すぎたりすると、空気の流れが悪く、通気性が保たれないことになります。

サイディングの剥がれ以外にも、汚れも目立ちます。
広範囲に黒っぽく広がっているものは、「気生藻(きせいそう)」と呼ばれる藻の一種で、藻が発生するということは、壁の保水力が強いことになります。
壁の凸凹部分や塗装の剥がれた部分などに水分が留まります。南向きの日当たりのよい壁面であれば、日射により湿気が解消され、藻の発生も抑制されることもあるでしょうが、日当たりの良くない方角の場合は、壁に付着した藻類が死滅せずに活性化することも可能で、その結果、藻類の増殖で壁一面に汚れが広がっていくことになります。
最終的には、サイディングを剥がして内部を確認しなければ、原因究明と解決にはなりませんが、それなりに大掛かりな工事になりそうです。
依頼主様には、現状をご説明し、さらなる調査をご希望される場合には、ご連絡いただくようにお伝えしました。
▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽
昔の木造建築では、断熱材を使用しないことも当たり前で、断熱や気密などをあまり重要視しない構造だったので、結露が建物に及ぼす問題もあまり注目されることはありませんでした。
ある意味風通しがよい構造だったので、壁の中に結露が派生しても通気により乾いてしまい問題にはなりませんでした。しかし、断熱材が普及したことにより内部結露が大きな問題になりました。
室内温度と健康被害の関連性がクローズアップされる昨今では、断熱材は重要な建材の一つとなっています。よって結露による被害を防ぐためにも、定期的なメンテナンスを是非お勧めします。
≫ここまでやります無料点検
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん東濃店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.